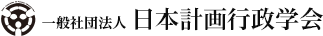研究論文・研究ノート・資料 投稿規定・執筆要領
投稿規定
1.[投稿資格]
原稿を投稿するには、著者の少なくとも一人が、正会員、学生会員であるか、または入会手続き済みであることを必須とする。
2.[原稿の種類]
投稿する原稿は、研究論文、研究ノート、資料とする。研究論文は、研究の学術的貢献が十分に認められ、論文としての完成度が高いもの、研究ノートは、論文ほど完成度が高くないが、機関誌に掲載することが有意義と認められるものであり、資料は、研究的価値は低いが資料として機関誌に掲載することが有意義と認められるものである。いずれも、査読を経て、それぞれの水準に達していると認められた場合に採択される。
ただし、審査の結果、研究論文として投稿されたものは、研究ノートまたは資料としてのみ採択が許可されることがある。また、研究ノートとして投稿されたものは、資料としてのみ採択が許可されることがある。
3.[投稿方法]
学会誌投稿エントリーフォームより電子投稿する。投稿時には、著者情報(和英)、連絡先、論文枚数を記入し、執筆要領に基づいて作成した原稿のpdfファイルをアップロードする。投稿後、数日中に受け付けの通知を電子メールで行うが、通知が来ない場合は学会事務局に問い合わせる。
4.[原稿の訂正]
原稿投稿後の訂正には応じない。
5.[重複投稿ならびに剽窃の禁止]
本学会または他学会等の審査付き論文集等に、同一の論文等を重複して同時に投稿することはできない。また、論文作成にあたっては、論文のオリジナリティを確保し、剽窃等により他者の著作権を侵害してはならない。
6.[研究論文の判定基準]
論文審査小委員会は、受け付けた原稿の審査を複数の専門家に依頼する。投稿論文採否の判定基準は、下記のとおりである。
(1) 論文の貢献(新規性、独創性、発展性、実務を含めた応用可能性、有益性、現象解明の諸点が十分であるか)
(2) 完成度(既存研究の参照と位置づけ、目的・成果の明確性、資料・データの適切性、論理展開・分析の適切性、文章表現・図表の適切性、全体構成が適切であるか)
7.[校正]
掲載が決定した原稿は、初校のみ著者に送付するので、速やかに校正し、指定の期日までに原稿を返送する。校正時における文章や図表の新たな追加・削除は認めない。
8.[掲載料]
掲載が決定した時点で、6頁までは1万円、それを超過する場合は超過する頁について2万円/頁をさらに追加して支払うものとする。研究論文の場合は、最大でも12頁とする。研究ノート、資料の場合は、最大でも8頁とする。研究論文、研究ノート、資料のいずれの場合においても、やむを得ない事情で超過する場合には、最大限度を超過する分について5万円/頁を追加で支払うこととする。
9.[既発表論文等の訂正記事]
学会誌上に既に掲載された論文等の訂正記事を出す場合は、日本計画行政学会事務局に訂正記事の原稿を著者連絡先の情報とともに送付することとする。訂正記事は論文審査小委員会において審査することとし、掲載が認められた場合には、日本計画行政学会に所定の掲載料をただちに支払うこととする。
訂正記事の掲載料は以下のとおりとする。
(1) 機関誌1/3頁(500字相当)までは無料
(2) 1/3頁を超えて1頁以内の場合は2万円
(3) 1頁を超えて2頁以内の場合は5万円
(4) 2頁を超える場合は追加1頁ごとに5万円を加算
よって、3頁では10万円、4頁では15万円などとなる。
10.本規程の改訂は学術委員会が審議し、理事会の承認を得て行うものとする。
(2014年1月1日改訂、2014年1月1日より施行)
(2016年1月1日改訂、2016年1月1日より施行)
(2016年8月4日改訂、2016年9月1日より施行)
(2024年7月30日改訂、2024年8月1日より施行)
(2025年3月31日改訂、2025年4月1日より施行)
執筆要項
1.[原稿]
原稿は学会ウェブサイトにあるテンプレート(Word)を利用して作成する。原稿分量は、和文の場合はワープロを使用し、A4版で23字×46行×2段(2116字)とし、英文の場合も、同様のスタイルとする。いずれも題名・アブストラクトを含む。
2.[著者の順番]
複数の著者による論文の場合には、論文への貢献度の大きい者から順に著者を列記すること。
3.[図表]
原稿分量には図表を含む。図表は原稿に挿入する。図、表それぞれに一連番号をつけ、図1・・・、表1・・・のような形で記載する。なお、図表は機関誌掲載時に約86%程度に縮小されることを考慮し、見やすさに注意することとする。
4.[英文アブストラクト]
研究論文の場合は、書式見本に従って英文アブストラクトを添付すること。アブストラクトの最後に、英語のキーワード/フレーズを、3~5語/句の範囲で記入する。
5.[参考文献]
参考文献を適切に引用し、本研究の位置づけを明確にすること。
参考文の引用は例に倣い、著者の姓、発表年を書く。
例:山田(1985)は・・・・・・、鈴木(1986a)によれば・・・・・・
・・・・・・が証明されている(山田・鈴木、1985)。
Tanaka et al (1980) は・・・・・・。
参考文献表は、本文末尾に著者のアルファベット順、年代順に記す。
同一著者の同一年代の文献は、引用順にa、b、c・・・・・・を付して並べる。
例:鈴木次郎(1986a)「計画と行政」、『計画と行政』17、34~43.
鈴木次郎(1986b)『計画論』学陽書房.
Tanaka, S. et al (1980) Planning Administration, Academic Press, New York.
Tanaka, S. (1981) “Formal theory of planning”, Mathematical Planning, 18, 121~138
山田太郎 (1985) 「計画行政に関する研究」、『計画と行政』13、44~50.
山田太郎・鈴木次郎 (1986) 『計画行政学』学陽書房.
(2014年1月1日改訂、2014年1月1日より施行)
(2016年1月1日改訂、2016年1月1日より施行)
(2016年8月4日改訂、2016年9月1日より施行)
(2024年7月30日改訂、2024年8月1日より施行)
(2025年3月31日改訂、2025年4月1日より施行)